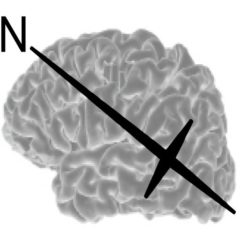JR北広島駅付近は東光ストアや飲食店など商業地域となっているが、もともとの市の中心街はおそらく駅から1kmほど離れた市役所のあたりであり、このエリアに「広島市街」というバス停がある。市役所の南東には「北広島市総鎮守 廣島神社」が建っている。その歴史は神社内にある「広島神社由緒」と題された鎮座百年記念碑に詳しい。
広島県の人和田郁次郎は、北の未開地に一村を開発しようという大きな志をいだいて単身北海道へ渡った。明治十六年四月のことである。途中、伊勢の國に立寄って、皇大神宮に詣で、開拓の成功を祈念すると共に、その御神霊を移住民のため守護神として申受けたのである。
この地を開拓適地と認めて準備を進めること一年余、翌十七年五月二十三日。故郷の広島県から最初の移住者十八戸の人達をむかえた。この時、和田郁次郎は開墾地の一角、小高い清浄な地を選んで小さな祠を建て、伊勢で申受けた御神霊を安置した。これが即ち現在の場所であり広島神社のはじまりである。
それ以来、広島開墾地の人たちは、最初の移住者が到着した五月二十三日を春祭と定め開村と五穀の豊穣を祈願し、十月十日を秋祭とし新穀を供へ感謝の誠を捧げてきた。
明治二十三年には移住者の数も百三十戸に増え、開拓も大いに進んだ。「これもみな御神徳のおかげ」と和田郁次郎は願主となって新社殿を建立し、この時、御祭神として大国主大神、事代主大神の二柱の神々を増祀したのである。
明治三十年、村民たちは力をあわせ「神社創立」を願い出た。翌三十一年それが許可となり、正式に
無格社広島神社として認められた。以来、広島村民は社殿を改築し、専従の社家を置き、社務所を建て、楢丸太造りの大鳥居を建て、更に神社財産を造成するなど広島村民の信仰を集めるにふさわしい規模を整えることに努めた。
そして明治四十三年、村社に加列され、翌四十四年には神饌幣帛料供進神社にも指定された。これからは、春秋例祭、神嘗祭の折には広島村長は衣冠束帯を身につけ、村政の一般を報告するとともに幣饌料を供進したものである。
大正二年には氏子の数は八百戸にもなり、村社に列せられて以来、村民の信仰も一段と深まったことなどからそれにふさわしい新社殿を建立することになった。再び和田郁次郎が大願主となり、総坪数四十坪、木造神明造りの新社殿が、九月に完成した。
その後も村民の信仰はますます深まり、昭和六年には、川田栄次郎、川田浅次郎の両氏から鉄筋コンクリート製の大鳥居が寄進されるなど神社経営も安定していたが、昭和二十年八月十五日の第二次世界大戦の終戦と共に社会情勢は一変した。村からの助成は失われ神社財産の多くは開放され、神社経営は苦悩を強いられることになる
宮司をはじめ総代一同はこの苦難に耐え、氏子の信頼のもとに神社神道の回復に努力した。
昭和二十七年、広島神社は宗教法人として認証され、昭和四十三年には社務所の改築も行われた。この間、昭和三十五年には秋祭が九月十二日に改められている。
昭和五十八年は広島神社が鎮座して百年になるところから、この日に備え記念する事業として老朽化した社殿の新築が計画された。そして、昭和五十五年、神明造り鉄筋コンクリート造り、床面積百三十二平方米の新社殿が完成、その年の十二月正遷座祭を厳かに取り行った。
それ以来、新社殿には参拝者の絶えることなく、春秋の祭典も賑やかに行われ、御神徳はますます宣揚され今日に至っている。

ちなみに「神饌幣帛料供進神社」とは、明治時代から第二次世界大戦終了まで続いた制度で、地方公共団体が「神饌幣帛料」を供進する対象となっていた神社のことである。